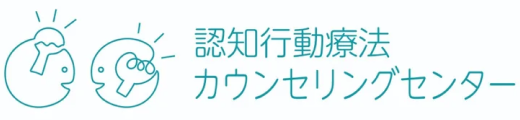2025年10月27日
- 認知行動療法
幼稚園の行き渋りは“子どもだけの問題”ではありません/認知行動療法カウンセリングセンター山口店

― 家庭でできる対応と、不登校を防ぐ視点 ―
1.朝の玄関で立ち止まる子ども
こんにちは、認知行動療法カウンセリングセンター山口店です。
ある朝、幼稚園へ向かう時間になっても、子どもがなかなか玄関から動きませんでした。泣きわめくほどではありません。けれど靴を履きかけては止まり、「まだ行きたくない」「おうちがいい」と小さく抵抗を示す。身体は前に進みかけているのに、足元にだけブレーキが掛かっている——そんな雰囲気でした。
その姿を見た私は、まず気持ちに寄り添うことを試みました。
「何か嫌なことがあるのかな?」
「少し疲れてるのかな?」
「今日はおうちにいたいんだね。」
親として、「まずは言葉を受け止めたい」という自然な反応だったと思います。
しかし、横で見ていた妻は、静かで揺るがない態度でこう声を掛けました。
「行くよ。」
淡々と、しかし確かに背中を押す声でした。
そのまま手を取り、玄関を出ていきました。
子どもは少し渋りながらもついて行き、幼稚園に着いてしまえば、いつも通り楽しそうに過ごしていたそうです。
この出来事から私が感じたのは、
「もし、私だけが毎朝対応していたら、おそらく今日の“行き渋り”は“行けない”へと育っていったかもしれない」
という実感でした。
2.“寄り添えばよい”わけではない理由
子育ての現場やSNSでは「子どもの気持ちに寄り添う」ことが、しばしば“正解”のように扱われます。もちろん、それが必要な場面もたくさんあります。
しかし一方で、「寄り添うこと」が 回避の後押し になってしまうこともあります。
- 行きたくない ⇒ 行かなくてよい
- 渋れば止めてもらえる
- 不安を出せば休める
このルートが成立すると、不安や行き渋りが“手放せない道具”に変わります。
本来「気持ちを言葉にする」は前へ進む力につながるはずですが、
援助の仕方によっては「回避の理由」として強化されてしまうのです。
ここで重要なのは、
「受け止めること」 ≠ 「回避を成立させること」
を混同しないこと。
そしてこの境界は、大人側の“意図”ではなく、
子どもにとっての“結果” で決まります。
3.子どもの行動は「個人」ではなく「関係」で立ち上がる
子どもの行動や感情は、子ども単体で生まれるわけではありません。
心理学ではこれを「相互作用」と呼びます。
- 誰がそばにいるか
- その人はどう反応するか
- その反応を経験すると次にどう振る舞うか
こうした循環の中で行動は形づくられます。
たとえば、
- 「甘えられる/止めてくれる大人」がそばにいれば、回避が強まることがある
- 「安心しながらも押し出してくれる大人」がそばにいると、挑戦に踏み出せることがある
同じ子どもでも、関わる大人が変われば「できる/できない」が変化するのは、そのためです。
4.“行けた”ことが自己効力感になる
この日の子どもは、幼稚園に着いてしまえば笑顔でした。
「ほんとうに嫌で行けなかった」のではなく、
✅ 迷い
✅ 甘え
✅ 不安の芽
✅ “行かない選択肢”を見せたい気持ち
このあたりの混ざり合いだったと考えられます。
そして、一度行けたこと自体が、「自分はできる」感覚を子どもに残します。
この“経験”こそが、次に踏み出す力になります。
この構造は、大人にも馴染みがあります。
- 面倒だから行きたくない → 行ってしまえば普通にやれた
- 不安だったけど参加したら楽しく終われた
私たちも同じ循環の中で生きています。
つまり、
「気持ちに寄り添う」は 入口、
「体験へつなげる」は 出口
であるべきなのです。
片側(寄り添い)だけだと、
“出口を失う”ことがあります。
5.行き渋りは、ゆっくり「構造」になる
行き渋りがこじれ、不登園や不登校につながるのは多くの場合、急ではありません。
“じわじわ”“気づかぬうちに”構造化します。
その仕組みを、もう少し丁寧にほどいてみると、
| 段階 | 子ども側の変化 | 家庭で起こること |
| 初期 | 「行きたくない」 | 休む/遅刻が成立する |
| 中期 | 「行けない気がする」 | 説得が長時間化 |
| 後期 | 「行かない」 | 家庭が“安全地帯化”する |
特に注意が必要なのは、
子ども自身が “自分の選択” だと思いこんでしまう段階です。
実際には「行けない」のではなく、
「行かなくても済む循環ができあがった」だけ。
ここまで進むと、本人の努力や気合いでは動けません。
“構造(関係+環境)”が固定化されたからです。
このように、行き渋りは「子どもだけの問題」のように見えて、
実際は 環境―子ども間の循環 が形づくる現象です。
だからこそ、
寄り添いだけでも、押し切りだけでも成立しません。
必要なのは“調整”です。
6.幼稚園段階は「まだ戻せる」柔らかい段階
行き渋りが生まれる背景には、不安・甘え・疲れなどさまざまな要素が混ざります。それらが“まだ固まりきっていない”のが幼稚園や保育園の段階です。この時期は「環境が変われば行動も変わる」可塑性(やわらかさ)が残っています。
ところが、小学校・中学校へ進むにつれて「学校生活=対人・集団・評価」の比重が大きくなり、行かない日が続くと次のような連鎖が起きます。
| 幼稚園 | 小学校以降 |
| 休んでも大きな差になりにくい | 一日休むと授業・宿題・集団関係が“穴”になる |
| 再スタートが比較的容易 | 「戻りづらさ」そのものが心理的不安要因に |
| 甘えと依存の線が曖昧 | 「自分はもう戻れないのでは…」という予期不安 |
つまり幼児期の行き渋りは「小さな失速」でも、小学校以降の行き渋りは「戻るための気力が要る」という質に変わります。ここが“不登校化の境界”といえる部分です。
7.不登校は「本人の意思」ではなく「構造化した回避」
多くの親御さんは、ある時点から「本人が行きたがらない」「意志の問題」と感じ始めます。しかし実際には、心理学的には真逆に近いです。
意思ではなく、**“回避が構造化してしまった結果”**です。
- 行かないことによって不安から一時的に守られる
- その経験が繰り返される
- 「行かない未来」が“一番安全な生き方”として脳に登録される
この構造が成立すると、
「行けないのではなく、“行けない方が自然になってしまう”」のです。
だから専門職は“説得”ではなく、
回避ではなく前進を選べる循環そのものを再設計します。
8.家庭で支えられる段階/支援導入の段階
では、家庭でできることと、外部支援が役割を担うべきラインはどこでしょうか?
| 家庭で支えられる段階 | 導入を検討したほうが良い段階 |
| 行き渋りはあるが登園はできる | 行かない期間が連続し始める |
| 登園後は楽しめている | 行かないことが“習慣”になり始める |
| どちらかの親の関わりで動ける | どちらが対応しても動けない |
| 休みは例外的 | 休みが「選択」になっている |
これは「親が頑張れない」から支援に頼るのではありません。
循環が固定したら、“第三の環境”が必要になるからです。
9.罪悪感が最も支援を遅らせる
ここで、多くの保護者が無意識に抱えるのが「罪悪感」です。
- もっと寄り添えたら違ったのでは?
- 無理に連れて行ったことが悪いのでは?
- 私の関わり方が間違っていたのでは?
しかし臨床的には逆です。
罪悪感は選択を狭め、「やさしさの名を借りた静かな回避」へつながります。
“自分が悪い” と感じると、
「次に踏み出す関わり方」を選べなくなるのです。
だから支援は、「何を間違えたか」ではなく、
ここからどう建て直すか
という地点から始まります。
責任ではなく再設計。これは治療的支援の根幹です。
10.「子どもを支える」とは“関係を支える”ことである
子どもの行き渋り・不登校支援は、
本人の性格を変えるものではありません。
子ども × 親(または家庭)の相互作用
= 行動を方向づける“循環”こそを見る。
だから本質は、
「子どもを支える」=「関係という環境を支える」
ということです。
11.まとめ:子どもの問題は「子どもだけ」で起きているのではない
親である私自身、今朝の小さな行き渋りを通して改めて実感しました。
- 行き渋りは“本人だけの問題”のように見える
- 実際には“関係の中で育っていく”
- そして対応のわずかな違いが未来の軌道を大きく変える
だからこそ、寄り添いだけでも、押し切りだけでもなく、
両方を行き来しながら「今の子に何が機能するか」を調律する姿勢が必要になるのです。
そしてもし家庭だけでは調律が難しくなった時には、
支援を「逃げ」や「弱さ」と捉える必要はありません。
むしろそれは、循環を閉じ込めず、
**新しい選択肢を開くための「第三の環境」**です。
子どもの問題は、子どもという個体の中だけで閉じて起きるものではありません。
家庭という“つながり”の中で生まれ、変化し、解消されます。
だからこそ、支援の焦点は――
「子ども」だけではなく、「子どもと大人の“あいだ”」
なのです。
【山口で不登校・行き渋りにお困りの保護者さまへ】
山口市・防府市・宇部市周辺で「幼稚園や小学校の行き渋り」「学校に行けない状態」「長期化する不登校」についてご相談を希望される方には、当センター山口店にて個別面談を受け付けています。
本人の“性格”だけでなく、親子の関わり方や家庭内の循環を丁寧に捉えながら支援を行います。
「今の状態はどの段階にあたるのか」
「家庭で支えるべきか、外部支援を入れるべきか」
判断の目安を知りたいというご相談も可能です。
【所在地】
〒753-0055 山口県山口市今井町4-10 山根ビル201号室
(JR湯田温泉駅 徒歩1分)
【WEBサイト】
https://yamaguchi.cbt-mental.co.jp/
【LINE相談窓口】
https://lin.ee/26sKHRK8
【お申込フォーム】
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
対面・オンラインとも対応しており、
保護者のみのご相談も可能です。