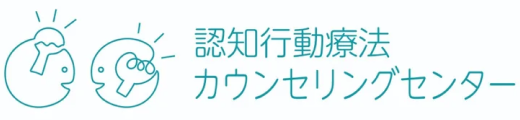2025年06月20日
- 認知行動療法
山口で考える“起立性調節障害”とカウンセリングの役割

朝がつらくて起きられない。
そのしんどさは、当人にしかわからないものがあります。
最近では、そうした子どもたちに「起立性調節障害(OD)」という名前がつくケースも増えてきました。
ここ山口でも、湯田温泉エリアを中心に、そうしたお悩みを持つご家庭からの相談が寄せられています。
本記事では、ODという診断名が持つ意味や議論、そして私たち心理支援の立場からできることについてお話しします。
起立性調節障害とは?症状とその背景
起立性調節障害(Orthostatic Dysregulation:OD)は、思春期に多くみられる自律神経の乱れを中心とした症状群で、次のような訴えが特徴とされています。
- 起きた直後に気分が悪くなる
- めまいや立ちくらみが頻繁に起こる
- 胸がドキドキする、頭が重い
- 日中の活動にエネルギーがわかない
医学的には、心拍数や血圧の変化を調べて「体位性頻脈症候群(POTS)」や「起立直後性低血圧」などの分類がなされることがあります。
しかし、身体だけを見ても全てが説明できるわけではありません。
心理的・環境的な要因が強く関わっていることもあり、医療と心理の橋渡しが求められる場面も少なくありません。
概念としての「OD」に対する疑問と配慮
起立性調節障害という概念そのものにも、医療や教育の現場から以下のような声があがることがあります。
- 国際的には診断名としての位置づけが曖昧
- 睡眠障害や心理的な課題との重なりが見られる
- 診断が逆に、回復のきっかけを遅らせてしまうこともある
たとえば、夜型の生活によって朝の活動が困難になる「睡眠相後退障害」や、抑うつ的な気分と結びついた無気力状態などが背景にあることもありえます。
また、「起きたくても起きられない」ではなく、「起きない方がいい事情がある」「学校に行くのが怖い」という気持ちが奥に潜んでいることも。
このように、ODは一つの「医学的ラベル」ではありますが、その中身はとても幅広く、画一的な対応が通用しない領域だと私たちは感じています。
山口で行うカウンセリングのアプローチ
認知行動療法カウンセリングセンター山口店では、診断名だけに注目するのではなく、「その子自身の今」に目を向けて支援を行っています。
たとえば、
- 「夜になると不安が強まって眠れない」
- 「学校の友人関係に悩んでいる」
- 「自分でも理由がわからないけれど、とにかく動けない」
こうした声に丁寧に耳を傾け、行動や思考の背景を整理していくのがカウンセリングのスタート地点です。
「ただのサボり」でも「気の持ちよう」でもない——
そんな思いを持ちつつ、回復に向けた第一歩を一緒に探していく時間を大切にしています。
よくあるご質問(Q&A)
Q1. 起立性調節障害と診断されました。どう受け止めればいいでしょうか?
A. 診断はあくまでひとつの手がかりです。症状の背景には生活習慣の乱れ、気持ちのつらさ、学校での不安などが関係していることも少なくありません。自分やお子さんにとって、何がしんどさの元になっているのかを、時間をかけて探っていくことが大切です。
Q2. 病院で「異常なし」と言われました。それでもカウンセリングを受けてもいいのでしょうか?
A. もちろんです。体には異常が見つからなかったとしても、「日常生活を送れないくらいしんどい」という状況に変わりはありません。カウンセリングでは、そうした“理由のつかないつらさ”にも丁寧に対応します。
Q3. 親として、どんな風に関わればよいのでしょうか?
A. 頑張れと言いたくなる気持ちを少しだけ横に置いて、まずは「何がそんなに大変なのか」を一緒に考えてみてください。本人が話せないときは、保護者の方からのご相談だけでも構いません。支援の第一歩は、“話していい”と思える安心感から始まります。
山口だからこそできる支援を
山口市の湯田温泉駅近くという立地から、学校や地域の医療機関とも柔軟に連携が可能です。
地域に根ざした形で、医療ではカバーしきれない心理的・社会的側面のケアを担うことが、私たちの役割です。
学校に戻るかどうかだけでなく、「今の生活をどう過ごすか」に寄り添える場所を、山口でも目指しています。
ご相談はお気軽にどうぞ
- 「うちの子に何が起きているのかわからない」
- 「病院には行ったけど、なにか他にできることは?」
- 「まずは話を聞いてもらいたい」
そんな時は、一度カウンセリングという選択肢を思い出してください。
山口店では、オンライン相談も可能で、顔出しなしの事前相談も行っています。
📍 認知行動療法カウンセリングセンター 山口店
🏠 〒753-0055 山口県山口市今井町4-10 山根ビル201号室
🚉 JR湯田温泉駅 徒歩1分
🕙 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
📝 Google口コミ:https://g.page/r/CTjhO6Kjpd35EBM/review
🌐 Webサイト:https://yamaguchi.cbt-mental.co.jp/
✅ LINEでのご相談:https://lin.ee/26sKHRK8
✅ 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
※本記事は医療的判断を否定するものではなく、心理支援の一助としての情報提供を目的としています。
一覧に戻る