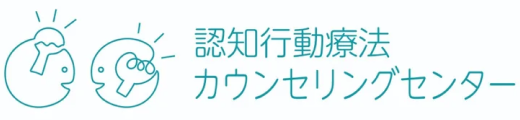2025年07月30日
- 認知行動療法
山口の養護教諭に役立つ認知行動療法

こんにちは。認知行動療法カウンセリングセンター山口店です。
今回は、学校で日々、生徒や保護者と向き合っておられる養護教諭の先生方に向けて、認知行動療法(CBT)の考え方が現場でどのように活かせるかをご紹介します。
養護教諭の現場で感じる難しさと、その支えになる考え方
生徒との会話、保護者とのやり取りの中で、次のような場面に心当たりはありませんか?
- 訴えの強い保護者への対応で戸惑ってしまう
- 保健室の利用が多い生徒の背景をどう捉えるべきか悩む
- ただ話を聞くだけでは限界を感じるときがある
こうしたとき、「心の整理」を支援するCBTの視点を持つことで、対応に余裕が生まれることがあります。
養護教諭が現場で活かせるCBTの3ステップ
CBTは医療専門職だけの技術ではなく、日常の会話の中でも取り入れられる実用的な考え方です。特に以下の3つのステップは、養護教諭の方にとって導入しやすいものです。
1. 「気持ち」と「体」の反応に気づけるようにする
まず、生徒自身や保護者が、その時に感じていた感情や体の反応に目を向ける機会をつくることが第一歩です。
- 「どんな気持ちだった?」
- 「体のどのあたりに反応があった?」
- 「それは、どんな考えが浮かんでいたからかも?」
これにより、相手が「自分に起きていたこと」に気づき、話しやすくなる関係性も築けます。
2. 行動の“意味”を理解する視点を持つ
繰り返される行動には、何らかの機能があります。たとえば:
- 不安を和らげるために保健室へ来る
- 話しながら涙を流すが、何度も同じ話を繰り返す
これらの行動は、一見「困った行動」に見えるかもしれませんが、短期的な安心感を得るための手段であることが多くあります。
CBTでは、行動を責めるのではなく、「どうしてこの反応が出ているのか?」と行動の“役割”に注目する視点を大切にします。
3. “他のやり方”を一緒に考えていく
CBTでは、無理に行動を変えさせることよりも、「気づいて」「自分で選ぶ」機会を作ることが重視されます。
- 「もし次に同じことが起きたら、どんなやり方ができそう?」
- 「こんな工夫もあるかも。どう思う?」
といったやり取りを通じて、本人の選択肢を一緒に増やしていきます。
保護者対応にこそCBTの視点を
保護者との面談で、感情的な表現に戸惑う場面もあるかもしれません。その際にも、CBT的な視点が活かされます。
- 「この保護者は、何に困っているんだろう?」
- 「どのような状況で不安が高まっているのか?」
- 「自分はどのような姿勢で対応すると落ち着けるか?」
このように、「言葉そのもの」よりも背景やパターンに注目する視点を持つことで、より建設的に話が進むこともあります。
こんな場面で役立つ!CBTの活用例
| 支援の場面 | CBT的な問いかけ | 効果・目的 |
| 保健室常連の生徒への対応 | 「どんなことがあった?どんな気持ちだった?」 | 背景の感情・考えに気づく支援 |
| 不安の強い保護者との会話 | 「どんなことが一番気になっておられますか?」 | 感情に巻き込まれず、信頼関係を築く |
| 繰り返される相談 | 「他にどんなやり方ができそう?」 | パターンに気づき、新たな選択肢へ |
よくあるご質問(Q&A)
Q1:心理の専門職ではないのですが、活用しても大丈夫?
A1:もちろん大丈夫です。CBTは“構え方・視点”が中心です。問いかけの工夫や捉え方を少し変えるだけで、支援の質がぐっと変わります。
Q2:保護者の感情的な反応に巻き込まれそうで怖いのですが…
A2:「反応の背景にある考えや不安」に注目する視点を持つことで、関わり方が変わり、落ち着いた対応につながります。
Q3:研修などで詳しく学べますか?
A3:はい。当センターでは、教育現場向けにCBT研修や勉強会の開催も承っております。ご希望に応じて内容をカスタマイズし、先生方が現場ですぐ使えるようサポートいたします。
認知行動療法カウンセリングセンター山口店のご案内
- 店舗名:認知行動療法カウンセリングセンター山口店
- 住所:〒753-0055 山口県山口市今井町4-10 山根ビル201号室
- アクセス:JR湯田温泉駅 徒歩1分
- 営業時間:10:00〜20:00(完全予約制)
- LINE:https://lin.ee/26sKHRK8
- 予約フォーム:https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSelm3nMBwOyvwnkhrkihe-APBzNTll2NL4fsPB6b6hHMzC8GA/viewform
- Webサイト:https://yamaguchi.cbt-mental.co.jp/
学校という多忙な現場において、“こころの整理”を促す問いかけは、支援の幅を広げるだけでなく、支援者自身の安心にもつながります。
「聞く」から一歩進んだ関わりを模索したい方は、ぜひ一度ご相談ください。
一覧に戻る