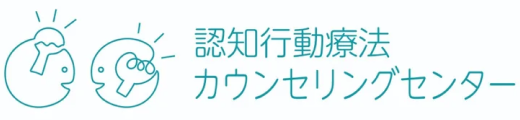2025年03月05日
- 認知行動療法
山口で過敏性腸症候群へのカウンセリング

身体と心のつながりを知り、対策を考える
「緊張するとお腹が痛くなる」「通勤中に急にお腹が気になる」「病院で異常がないと言われたのに、ずっとお腹の不調が続く」――このような経験をしたことはありませんか?
過敏性腸症候群(IBS)は、腸に明らかな病変がないにもかかわらず、腹痛や下痢、便秘などの症状が続く状態を指します。特に、ストレスや不安を感じたときに症状が悪化しやすいのが特徴です。
「ストレスが関係しているなら、気にしなければいいのでは?」と思うかもしれません。しかし、実際には「気にしないようにしよう」とすればするほど意識してしまい、症状が強くなることもあります。
では、どのように対策を考えていけばよいのでしょうか?
過敏性腸症候群の症状とタイプ
過敏性腸症候群は、大きく以下の4つのタイプに分かれます。
- 下痢型:急な腹痛とともに水のような便が出る。特に、仕事や学校などの緊張する場面で起こりやすい。
- 便秘型:お腹が張り、便がなかなか出ない。排便してもスッキリしない感じが続く。
- 混合型:下痢と便秘を繰り返す。日によって症状が変わるため、対策が立てにくい。
- 分類不能型:下痢や便秘以外の不調が続くが、はっきりとどのタイプとも言えない。
どのタイプでも共通するのは、腸が敏感になっていることです。特に、ストレスや生活リズムの乱れが影響しやすく、無意識のうちに症状を悪化させる行動を取ってしまうこともあります。
なぜ症状が続くのか?
過敏性腸症候群の原因は、まだ完全には解明されていませんが、次のような要因が関係していると考えられています。
1. 腸の動きの変化
腸は食べ物を消化しながら、一定のリズムで動いています。しかし、過敏性腸症候群の人は、このリズムが乱れやすく、必要以上に活発になったり、逆に動きが鈍くなったりします。その結果、下痢や便秘が起こります。
2. 腸と脳の関係
腸は「第二の脳」と呼ばれるほど、自律神経の影響を受けやすい臓器です。強いストレスや不安を感じると、脳が腸に影響を与え、過剰に反応しやすくなります。「またお腹が痛くなったらどうしよう」と考えると、それ自体がストレスになり、症状が悪化することもあります。
3. 習慣化された行動
例えば、「電車に乗るとお腹が痛くなる」「会議の前には必ずトイレに行く」といった行動が続くと、脳が「この状況=お腹が痛くなる」と学習してしまうことがあります。これが無意識のうちに繰り返されることで、症状が慢性化することもあります。
まずは自分の状態を知る
過敏性腸症候群の対策を考えるときに大切なのは、「なぜ自分の症状が続いているのか?」を整理することです。
例えば、以下のようなポイントを振り返ってみましょう。
- どんなときに症状が出やすいか?(時間帯、場所、状況など)
- 何を考えているときに症状が悪化するか?(不安、緊張、焦りなど)
- 症状が出たとき、どんな行動を取るか?(トイレに行く、食事を控える、予定をキャンセルするなど)
こうした振り返りをすることで、「自分の症状のパターン」が見えてきます。このパターンが分かると、「どうすれば少しでも楽になるか?」を具体的に考えやすくなります。
できることから始めてみる
過敏性腸症候群は、一度にすべてを変えようとすると負担が大きくなります。少しずつ、できることから始めてみましょう。
1. 生活リズムを整える
食事、睡眠、運動のバランスを整えることが、腸の調子を安定させる第一歩です。特に、朝食をしっかりとることで、腸の動きを整えやすくなります。
2. 「すぐにできる対策」を持つ
例えば、「電車に乗る前に深呼吸をする」「不安になったらガムを噛む」など、自分に合った対策を見つけておくと、少しずつ安心感が増えていきます。
3. 無意識の行動を見直す
「症状が出るのを避けるためにやっていること」が、逆に不安を強めていることもあります。例えば、「常にトイレの場所を確認する」「食事を極端に控える」などの行動が、症状を強化しているケースもあります。
最後に
過敏性腸症候群の悩みは、一人で抱え込むと「どうすればいいか分からない」「また同じことを繰り返してしまう」と感じやすくなります。
認知行動療法カウンセリングセンター山口店では、過敏性腸症候群の方へのサポートも行っております。
「ずっとお腹の調子が悪くてつらい」「なんとかしたいけれど、どうすればいいか分からない」という方は、ぜひ一度ご相談ください。
認知行動療法カウンセリングセンター山口店
一覧に戻る